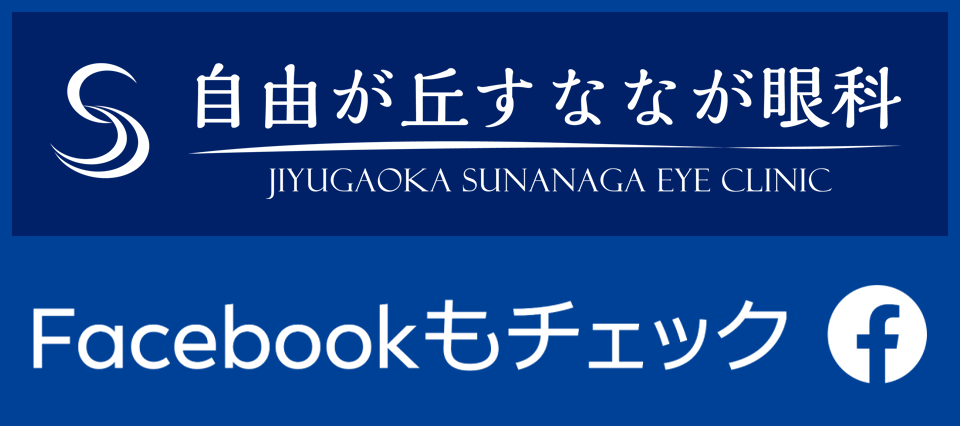診療内容
眼科一般
屈折異常
近視
近くのものが良く見え、遠くのものは見えにくい状態です。
メガネ、コンタクトレンズ装用でよく見えるようになります。
《近視の原因》
1.遺伝
2.環境因子:長時間の近方作業(読書、ゲーム、スマートフォンなど)
遠視
遠視は、「遠くが良く見える」のではなく、遠くも近くもぼやけて見えにくい状態です。
遠視が問題になるのが、子どもの場合です。
生まれたときには遠視の状態で生まれてきます。
遠視の度数が強かったり、左右の度数に差があると、斜視や弱視といった状態になります。
特に近くを見るときにはピントを合わせるのに苦労します。
このような場合は裸眼視力が良くてもメガネをかけた方が楽です。
斜視
眼位異常。まっすぐ向いた時に、片眼の位置が目標とは別の方向に向かっている状態です。
原因は、屈折に伴うもの、目の筋肉・神経異常に伴うもの、脳の病気、全身の病気など多岐にわたります。
弱視
眼鏡をかけても視力がでないこと。視力は、生後少しずつ発達していき、3歳くらいで視力検査が可能となります。
7歳頃までに両眼視機能が完成すると言われています。
乳幼児期に屈折異常(遠視・近視・乱視)や斜視により物が見えにくい状況が続いた場合、視力が正常に発達せずに弱視になることがあります。
3歳をすぎたら一度眼科での視力検査をおすすめいたします。
麦粒腫・霰粒腫
麦粒腫(バクリュウシュ)<ものもらい>
まぶたの皮脂腺や汗腺に細菌が感染して起こります。
まぶたが赤く腫れ、痛みがあります。
霰粒腫(サンリュウシュ)
麦粒腫と似た、症状の霰粒腫は、マイボーム線がつまってまぶたにしこりができる病気です。
痛みはありません。細菌感染を起こすと痛みを伴います。
治療:しこりが大きい場合は、手術により切除します。
ドライアイ
ドライアイとは、「様々な要因による涙液および角結膜上皮の慢性疾患であり、眼不快感や視機能異常を伴う」とされています。
ドライアイは大きく2つに分けられます。
1.量的な異常:涙の分泌量が減る状態です。
2.質的な異常:涙の成分異常(脂質成分、ムチン(タンパク質)、角結膜上皮異常)により涙が目の表面にとどまらずに、乾いてしまう状態です。
症状
○乾く○疲れる○ゴロゴロする○充血する○流涙○コンタクトレンズが痛いなど
検査
涙液分泌試験
涙の分泌量を調べる検査です。専用のろ紙を下まぶたにはさみ、5分でどのくらいの涙が出ているかを測定します。
細隙灯顕微鏡検査
フルオレセインという染色液を少量使用し、傷の具合、涙の安定性を調べる検査(BUT時間:涙液層破壊時間)をおこないます。
アレルギー性結膜炎
☆スギ花粉症の時期を過ごしやすくする為に~初期療法~
『初期療法』とは、花粉が飛び始める2週間前からまたは症状が少しでも現れた時点から、治療(抗アレルギー点眼薬)を開始し症状を軽くする方法です。
アレルギー検査について
当院ではアレルゲン(アレルギーをおこす物質)を特定する血液検査を実施しております。お子様でも検査可能ですので、お気軽にご相談ください。
※アレルゲン検査項目8種類(「花粉系」スギ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ(花粉飛散時期以外でも検査可能) 「ハウスダスト系」ネコ、イヌ、ヤケヒョウヒダニ、ゴキブリ)
※検査判定所要時間20分 (検査当日に結果をお知らせ)
※保険適用検査 (マル乳・マル子等医療証適用)
(検査費用3割自己負担 2,600円程度)
・季節性:春/スギ花粉、ヒノキ初夏/カモガヤ、オオアワガエリ秋/ブタクサ、ヨモギなど
・通年性:ハウスダストなど
ウィルス性結膜炎
感染力の強いウィルスによっておこる結膜炎です。
代表的なものとして、はやりめ(流行性角結膜炎)、咽頭結膜熱(プール熱)、急性出血性結膜炎があります。
感染した人の涙や手から接触感染します。
症状
メヤニ、充血、まぶたの腫れ、流涙、出血
種類
・はやり目(流行性角結膜炎):アデノウィルス 潜伏期間/7~14日
・咽頭結膜熱(プール熱):アデノウィルス 潜伏期間/5~7日
・急性出血性結膜炎:エンテロウィルス 潜伏期間/1~2日
経過
目薬で治療開始しても1~2週間は、症状が続くこともあります。
合併症
症状が改善する時期に、黒目に白い混濁を残してしまうことがあります。
これが原因で視力低下となることがあります。
適切な時期まで治療が必要です。
注意事項
流行しないように感染予防が大切です。 手をよく洗いましょう。
各診療内容の詳細については以下よりご覧ください
≫ 眼科一般≫ 白内障≫ 緑内障≫ 網膜硝子体疾患(糖尿病網膜症・加齢黄斑変性・飛蚊症など)≫ 小児眼科≫ 眼鏡処方・コンタクトレンズ≫ 近視進行抑制治療≫ 各種健診(世田谷区健診(眼底検査)・学校健診)≫ 往診